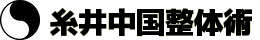- ホーム
- ブログ
ブログ
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
2024/12/01
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?
股関節のつまりとは?
股関節をまっすぐ曲げた時や股関節をまっすぐ曲げてから太ももを内側に倒したりすると、股関節の前のつけ根につまるような圧迫感、ひっかかりのような感じの状態のことです。
しゃがむ動作で股関節を深く曲げる、座ったまま上半身を捻るなど股関節を内側へ閉じる捻る動作になったときに感じやすいです。
また、つまり感が強い場合は車の乗り降りや階段の上り下りなどでもつまりを感じることがあります。
このつまり感は、股関節周囲の筋肉が硬くなっていることによって起こっています。
しかし、股関節周囲の筋肉が単に硬くなっているだけではなく、股関節周囲の筋肉がバランス良く力を発揮することができなくなり、支えることが弱くなってしまったさぼり筋の影響をうけて、筋肉が過剰に頑張って硬くなってしまっているのです。
筋肉が硬くなってしまうと、股関節の動きが制限されてしまうのでスムーズに動かせなくなってしまい、つまりを感じてしまいます。
つまり感の原因として多いのは、腰椎から大腿骨の内側に着く大腰筋(だいようきん)と骨盤の内側から大腿骨の内側に着く腸骨筋(ちょうこつきん)、この2つの筋肉を合わせた腸腰筋(ちょうようきん)が代表的です。この腸腰筋が硬くなることで大腿神経が圧迫されて、つまるという感覚が起きてしまいます。
股関節がつまる原因は?
・不良姿勢
・運動不足
・立ちっぱなしなど股関節に負担がかかる作業
・股関節の筋力不足
股関節のつまりは、ストレッチに運動をプラスするとさらに効果UP!
SNSでもたくさんのストレッチ方法が紹介されています。
股関節をストレッチすることも大事ですが、もっと効果を出すなら股関節を動かす運動を取り入れるとなお良いでしょう。
①椅子に座って、両方のつま先を内側へ向ける
②両膝の間は、こぶし1個分空けて、太ももの内側を意識してそのまま足踏みをします。さぼり筋改善トレーニングで、さぼり筋が働くようになってくると、硬くなってしまっている筋肉はその影響を受けて頑張りすぎず緩んできてくれます。
股関節は、いくつもの筋肉で支えているので、ひとつでも筋肉が支えることをサボってしまうといろいろな症状が出てきてしまいます。
-
 ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
-
 股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
-
 膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
-
 アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
-
 インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
糸井中国整体術
当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。
| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |
| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |
| 定休日 | 不定休 |
| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |