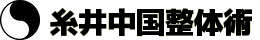- ホーム
- ブログ
ブログ
太ももの内側の筋肉「内転筋」が使えていないとどうなる?
2026/01/31
今月は、股関節と太ももの内側をつないでいる筋肉「内転筋(ないてんきん)」について書いていきます。
使えているかどうかの簡単なセルフチェックは、
・片足立ちをしてみて、からだがグラグラとふらついてしまう。
・椅子に座り、両脚をそろえ、内ももに力を入れてしばらく脚を閉じた状態にします。このとき、脚を閉じ続けられない、内ももが疲れる場合は、内転筋がうまく使えていない状態です。
重要な筋肉にも関わらず、なぜ使えなくなってしまうのか?
それは、日常生活の習慣が大きく影響しています。
そのひとつが、座りすぎによる影響。日本人は、世界で一番座っている時間が長い人種です。
長時間座りっぱなしでいると、股関節はほとんど動かさないために固まりやすくなります。
さらに内転筋(特に大内転筋)が伸びたままの状態で、使う意識がおろそかな状態で日々くり返されることで気づかないうちに使えなくしてしまっているのです。
また、足を組むクセも要注意で、骨盤を歪ませて、片側の内転筋ばかりに負担をかける状態を自ら作り出して使えなくしてしまっています。
歩いているときにも内転筋が正しく使えていないことで歩行動作に現れてきます。
ガニ股歩行、内股歩行、腰が反っている、腰が丸くなっている姿勢で歩いていることです。つまり、腰、股関節、膝関節に負担をかけ続けている状態になってしまいます。
これは、姿勢を支えるために必要な筋肉同士の連携、バランスが崩れているために起こり、結果的に歪み、痛みの原因になってしまいます。
・股関節の柔軟性が低下し、脚をスムーズに動かしにくくなります。
・股関節の可動範囲が狭くなり、脚が開きにくい、閉じにくくなります。
・骨盤が後ろに傾きやすく、姿勢が丸まりやすくなります。
・歩いているとガニ股になりやすいです。
内転筋は日常生活で使われにくいため、硬くて弱い筋肉になっている方も多いです。
痛かった「頚椎症」の症状が治りました!
2026/01/01
先月のブログで「頚椎症」になってしまったことを書きました。
なので、セルフケアは今までよりもかかせなくなりました。
診断された名称は「頚椎症性神経根症」で発症したときは本当につらかったです。
顔を上に向けたり、左右に向けたりすると首から肩までズキッと激痛が、腕から指先まではズキンそしてビリビリとした神経症状に苦しめられました。
足で例えるなら、きつい坐骨神経痛みたいな感じでしょうか。
体を酷使する人に限らず、日常生活の何気ない習慣が原因で発症することがあり、特に症状を感じないから「自分には関係ない」と思っていると突然やってくるので、決して他人事ではありませんよ。
それは、スマホやパソコンを見るといった日常生活にかかせない習慣が影響しているからです。
初期症状は、肩甲骨の内側や背骨のすぐ横、首の後ろから肩や腕、指先にかけての痛みやしびれ、肩甲骨周囲が凝った感じといった症状です。
首を後ろに反らすと痛みやしびれが強くなりますし、顔を横に振り向くのでも痛みが出ます。唯一、顔を下向けるのは症状がほとんどありません。
車の運転も左右確認がつらかったですし、私はバイクにも乗るので、ヘルメットの重さがかかるだけでも症状が増してきたので乗ってられませんでした。
こうしたつらい症状は、単なる「肩こり」や「寝違え」だと思ってしまう方も多いのではないでしょうか?
この症状を放置すると、筋力低下や神経麻痺など、さらに重い症状につながって手術を勧められてしまう可能性もあるので、楽観視しないほうが良いですよ!
では、今回このような激痛症状が出て私の場合どうやって治したか?
通院リハビリは、クリニックの診療体制上、週1回(リハビリ実施時間20分)しかリハビリ枠が取れませんでした。
なので、メインとなる治療は自宅でのセルフケアがすごく重要となってきます。
ここからセルフケアについて書いていきます。
さぼり筋改善トレーニングは、肩甲骨の中から脇の下の肋骨に付く前鋸筋、肩甲骨の内側から胸椎の上の方に付いている菱形筋、腕の後ろにある上腕三頭筋を意識して力を入れることを毎日していました。
首の筋力強化については両手の平を後頭部に当て、顎を引いて頭を後へ手の平で押し合うようにして、首の前を支える筋肉を鍛えました。
さらに右手を右の側頭部に当てて、頭が動かないように手と頭を押し合うようにし、左側も同様にしました。そして、顔を上に向けても痛みや腕の外側にビリビリ走っていた神経症状も完全に消えてしまったため、リハビリ卒業しても良いかどうかの診察を受けた結果、頚椎症性神経根症の治療終了の診断をしていただくことができました。
頚椎症(けいついしょう)になってしまいました
2025/12/01
そのため、炎症が治らないうちに首にさらなる負担がかかり、痛みや凝りの再発を繰り返して慢性化してしまいます。
首こり肩こりも、単に使いすぎて負担がかかっているだけでなく、使えていない筋肉の影響を受けて使いすぎているので、硬くなっている筋肉を緩めたり、ストレッチだけして満足していてはダメで、使えていない筋肉(さぼり筋)を使えるようにしていくことを運動療法で対策していくことが根本改善になっていきますし、再発防止にもなっていきます。
毎日なにげに足を組んで座っている姿勢。
その理由と身体への影響はあるのでしょうか?
2025/09/16

突然ですが、みなさんは足を組む姿勢についてどう思われていますか?
日々の生活で、椅子に座ると無意識に足を組んでしまう、長時間同じ姿勢でのデスクワークで腰やお尻がつらくなってきて足を組んでしまうという方は多いのではないでしょうか?
一見、特に問題はなさそうに見える姿勢ですが、足を組むクセがついてしまうと、背骨や骨盤を自ら歪ませるだけでなく、脳にまで悪い姿勢を記憶させてしまうということを知っていましたか?
特に症状がないからと思って歪みをそのままにしておくと、関節の動きが少しずつ異常をきたし、積もり積もった歪みの負担が痛みや凝り、疲れがなかなかとれないなど、身体のあらゆる不調につながりかねません。
椅子に座ると足を組んでしまう、やめようと思っていても無意識に組んでしまう。。。なんで?
●同じ姿勢のつらさを和らげようとしている
ずっと同じ姿勢で長時間座って仕事や作業をしていると、座面に接しているお尻や腰などがつらくなってきます。
つらいと感じるとじっとしていられず、楽な姿勢を探そうと座り直したり、足を置く位置を変えてみたりしていませんか?
お尻や腰のつらさを少しでも軽減しようとするために、足を組むと片側のお尻にかかっていた荷重を浮かせられるため、同じ姿勢からくるつらさを軽減することができるからなんです。
また、背筋を伸ばして座るのもつらくなるため、足を組んだまま背もたれに寄りかかって尾骨や仙骨で荷重を受ける座り方、または前にかがみこんで猫背の姿勢になったりしてしまいます。
つらさを和らげるために、足を組んでしまっているんです。
●バランスの悪さ・姿勢の悪さを改善しようとしている
座った直後に足を組んでしまう方は、座ったときのバランスの悪さや、姿勢の悪さからくるつらさを和らげようとするために、足を組んでしまうことがあります。
バランスが悪いということは、椅子に座ったときに骨盤が安定しないため、足を組んでバランスをとろうとしているのです。
つまり、足を組まないで座ると違和感を覚えて居心地が悪いと感じ、足を組んで骨盤と背骨を歪ませている状態が座り心地が良い状態、正常と認識しているのです。
逆の足を組むようにするとバランスがとれて安定するのではないかと思ってしまいますが、そう簡単に都合良くバランスがとれるものではありません。
姿勢の歪みを繰り返してしまう悪循環になってしまうでしょう。
足を組むとどんな悪影響があるの?
1.骨盤のバランスが悪くなる
足を組むと一時的に姿勢は楽になりますが、バランスが崩れたまま長時間座り続けると坐骨の片側に負担がかかり、つらくなると足を組み替えたりしてバランスをとろうとします。
足を組んでいるときの骨盤は、上下・左右どちらにもねじれており、バランスを崩した不自然な姿勢になっています。
それが毎日の積み重ねで腰痛や肩こりなどあらゆる不調を引き起こす原因になってしまいます。
これを放置していると疲れが取れにくくなり、腰や背中、自律神経などの不調も誘発してしまいます。
骨盤の歪みで腰痛を発症し、整体に行っているけど、普段の生活で無意識に足を組んでいることが当たり前のように続いていると、施術だけでは腰痛症状がなかなか改善しにくい場合も十分考えられます。
症状を感じないからと放置しておくことが一番身体に悪いです。
2.腰痛や首こり肩こり、頭痛、自律神経症状などを引き起こすきっかけにもなる
つらさを和らげようと足を組むことがきっかけで骨盤の左右差が少なくても身体全体の歪みへつながります。
両方の足を組めるから歪みがないとは限らず、実際には左右ともに傾いている場合も少なくありません。
3.身体全体の血流など循環系が悪くなる
日常的に足を組む姿勢の積み重ねで筋肉が硬くなると、身体の血流も悪くなります。
血流が悪くなると臓器を含めた身体全体に酸素が運ばれにくくなり、酸欠状態に陥ってそれが筋肉や神経への痛みや慢性疲労のもとにもなってしまいます。
また、脚のラインが崩れ美脚から遠のいてしまうといった美容への悪影響にも発展してしまいます。
4.ポッコリお腹や太もものたるみになる
前述した3つと関連して、骨盤は内臓を支える役割があります。
骨盤が歪むと腰、お腹、股関節周囲の筋肉は硬くなって頑張りすぎている筋肉と骨格を支えることをサボってしまっている筋肉の影響を受けて、内臓を支えられなくなってしまいます。
特に腹横筋は内臓をコルセットのように包んでくれる役割があり、またサボりやすい筋肉でもあるため、歪みと相まってお腹がポッコリ出てしまいます。
足を組む姿勢は筋肉を硬くするだけでなく、使うことをサボらせて弱らせてしまうことにもつながります。
足を組むのをやめる対策は?
こうした不調を防ぐためには、無意識のクセを自覚して、日常的に足を組まないように心がけましょう。
もし、足組みに気づいたら深く座り直し、骨盤を立ててお尻を背もたれに密着させ、背筋を伸ばすようにしてみてください。
座った姿勢につらさを感じたら、足を置く位置を少し変えたり一度立ち上がるなど、お尻にかかっている圧を解放して休憩を入れるのも必要です。
理想の座り方
1.椅子に深く座り、骨盤が立つように、腰を背もたれに密着させると背中もつくので背筋を伸ばしやすくなります。
2.両足の裏全体が床につく高さになるように調整します。
3.坐骨に体重をかけるイメージで左右均等に体重をかけるように意識してみましょう。
ストレッチをすることも有効ですが、それはあくまでも痛いところを施すその場しのぎの対症療法なので症状は必ず戻ってきてしまいます。
当院が推奨している、さぼり筋改善セルフケアを続けると、サボっている筋肉が目覚めて関節を支えられる力がつき、硬くなりやすい筋肉は硬くなりにくくなり根本改善が期待できます。
これを機に座り方を見直して足組みの回数を減らすだけでも、歪みの蓄積と身体への悪影響を減らしやすくなりますよ。
さらに、定期的に整体に行ってる場合なら、なかなか改善しない症状が改善出来る可能性だってありますよ。
インナーマッスルが重要な理由
2025/09/01
身体を動かす際に大きな力を発揮したり、関節を動かしたり、骨を守る重要な役割を持っています。
インナーマッスルは、身体の奥深くにある筋肉のことで「支える筋肉」と言われています。
関節の動きの安定性や内臓を支える働き、姿勢を保つために欠かせない筋肉で重要な役目を果たしています。インナーマッスルを鍛える5つのメリット
1.体幹を安定させる
背骨の周りに位置する筋肉(多裂筋、腹横筋など)が働くことで胴体を安定させて、日常の動作や運動時にバランスを維持します。
2.姿勢の維持
脊柱や骨盤周りに位置する筋肉(多裂筋、骨盤底筋など)が不安定なポジションでも適切な姿勢を保てるように調整します。
3.呼吸のサポート
横隔膜は呼吸時に働く重要なインナーマッスルです。腹横筋の働きが弱くなると腰痛だけでなく、横隔膜の動きにも影響するため浅い呼吸になってしまい、それが努力性の呼吸になることで首の筋肉の緊張が増して首こり肩こりの要因にもなってしまいます。
4.骨盤の安定性
骨盤の前を支える腸腰筋、骨盤の後ろを支える多裂筋や腹横筋、骨盤の底部を支える骨盤底筋があります。どの筋肉も弱ると骨盤が歪み、腰痛などの元になります。
5.関節の安定性
関節の奥にある筋肉が正常に働いていると、関節は正常な動きと安定性が確保できるため、動作がブレることなくスムースに動かせたり、姿勢を保持することができます。
インナーマッスルの主な種類
●回旋筋腱板(かいせんきんけんばん)ローテーターカフとも呼ばれ「棘上筋」「棘下筋」「小円筋」「肩甲下筋」という4つの筋肉から構成されている肩のインナーマッスルで、肩関節を安定させる役割があります。
回旋筋腱板を鍛えると、肩関節が安定してスムーズに腕を動かせるようになります。
肩関節の安定性が重要なスポーツでのパフォーマンス向上に大きく貢献し、また、怪我のリスク軽減や四十肩・五十肩の予防にもつながります。
上半身と下半身
●腸腰筋(ちょうようきん)上半身と下半身をつなぐインナーマッスルです。
腰椎から太ももの内側にかけて付着している筋肉で、骨盤を支えながら股関節を曲げる役割があります。
デスクワークなどで長時間座った状態を続けていると腸腰筋が硬くなりやすいです。
腸腰筋を鍛えることで姿勢維持の力が鍛えられるため、腰痛の予防改善につながります。
また、歩く時に使われる筋肉のため、つまずき防止の効果もあります。
下半身
●多裂筋(たれつきん)首から腰の脊椎にかけて背骨に沿うように存在するインナーマッスルです。背骨を安定させて正しい姿勢を維持したり、腰や腹部を安定させたり、体幹部を回したりする時に使われます。
多裂筋を鍛えると、背骨が安定して猫背の改善・美しい姿勢をキープできるようになります。同時に腹部も安定するため、腰痛と怪我の予防になるというメリットもあります。
頸椎、胸椎、腰椎といった背骨のズレは多裂筋や以下にある腹横筋、腸腰筋などの支える力が低下しているためにズレが生じて歪みとなっています。
●腹横筋(ふくおうきん) 腹筋の一番深い場所にあるインナーマッスルで、肋骨から骨盤までの広範囲に位置し、コルセットのように腹部を覆って内臓を支える役割と腹部内圧を高める役割があります。
腹横筋を鍛えることで、背骨が安定して腰痛改善につながり、内臓が正しい位置に戻り、下腹部がすっきりするメリットがあります。
●骨盤底筋群(こつばんていきんぐん) 骨盤の底にあり、子宮や内臓を支える大切な筋肉群で尿道や肛門、膣周りのインナーマッスルも骨盤底筋です。
骨盤底筋には内臓を下から支えて正しい位置を保つ役割があるのですが、加齢や妊娠、出産によって衰えやすい筋肉群です。
骨盤底筋を鍛えるメリットは、尿もれの予防・改善だけにとどまらず、自律神経を整え、血液やリンパの流れを促すことで、不眠・冷えなどの不調改善にも役立ちます。
骨盤の底を支えてくれるので、体幹が安定して姿勢が良くなることで、肩こり・腰痛の予防改善にもなります。
鍛え方
アウターマッスルだけを鍛えるとどうなるのか?
インナーマッスルは機能しなくなり、使いすぎているアウターマッスルの影響で、関節の動きが不安定になり、何か動作をしたタイミングで怪我をしやすくなったり、関節のズレとなって痛みを発症したり、疲れやすくだるさや倦怠感の原因にもなったりします。
つまり、肩、腰、膝などの関節が不安定になると、筋力は強くても無理な動きによって捻挫や筋肉の損傷が起こりやすくなってしまうのです。
鍛えるには、アウターマッスルとインナーマッスルのバランスを取ることも重要になってきます。
インナーマッスルとアウターマッスル、どっちを先に鍛えると良いの?
インナーマッスルから鍛えることで、アウターマッスルの種目が安定して運動効果が高まります。
アウターマッスルを先に鍛えると、インナーマッスルのトレーニング時も表面の筋肉に力が入りやすくなり、深部への効果が感じにくくなってしまいます。
身体を痛めてしまう人と痛めない人には必ず身体の使い方に違いがある
それは、筋肉に力が入る順番です。
身体を痛めてしまう人は、先にアウターマッスルに力が入り、次にインナーマッスルに力が入るかサボって機能していないかです。
インナーマッスルに力が入らない状態でアウターマッスルに力が入ると、関節が安定していない状態で急に動かされるために、ぎっくり腰やヘルニア、寝違え、五十肩など様々な症状の原因となります。
つまり、ギックリ腰を繰り返す方は、インナーマッスルが機能していないということです。
反対に、痛めない人は先にインナーマッスルに力が入ってからアウターマッスルに力が入ります。
関節が安定してから動くので筋肉にも負担が少なく、よほどの無理をしない限り痛めることはありません。
関節痛があると、首、背中、腰または骨盤をボキボキ鳴らすと気持ちが良くて、関節のズレが矯正されたと思いがちですが、それは一時的に矯正されているだけで、実際はインナーマッスルが働いていないので時間が経つことで関節は再びズレが再発してきてしまいます。
筋肉を揉んだり、ストレッチしたりでは足りません。
面倒くさい、効いてる感がないから無意味と思っていると、いつまでも慢性症状などの付き合いになってしまいます。
慢性症状などの戻りをなくし、根本改善するならインナーマッスルを使えるようにしてみてはいかがでしょうか?
今月も最後まで読んでいただきありがとうございました。
アイススラリーって知ってますか?
2025/08/01
毎日暑いですね。
アイススラリーは、コンビニやドラッグストアでも販売されていますし、自分で作ることも可能です。
自分で作る方法
ミキサーまたはハンドブレンダーで作る方法
【作り方】
①スポーツドリンク300mlを冷凍し、残り200mlは冷蔵庫で冷やしておきます。
②凍ったドリンクと冷やしたドリンクをミキサーに入れ、全体がなじむまでミキサーやフードプロセッサーで撹拌します。
③シャーベット状になったらアイススラリーのできあがりです。
ちょうど良いシャリシャリ感を目指してみてください。ミキサーなしで作る方法
【作り方】
①スポーツドリンク等を冷凍用保存袋に入れて、冷凍庫で3〜4時間ほど冷やします。
②完全に凍らせず、シャリシャリとした状態で取り出します。
③スプーンやフォークで軽くほぐせば、アイススラリーの完成です。
冷凍庫の設定や室温によって凍る時間は変わりますが、途中で様子を見ながら“半解凍”くらいを目指すと、ちょうど良いシャリシャリ感になります。
ペットボトルで作る方法
【作り方】
①冷蔵庫に入れているスポーツドリンクを冷凍庫に約2時間入れておきます。
②約2時間後、冷凍庫から取り出したペットボトルの底をキッチンの台などにドンっと当てて衝撃を加えてから、強めにシェイクします。
③まだ凍っていなかったスポーツドリンクが過冷却水の効果で、ゆるめのシャーベットになったらできあがりです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
膝が痛い!原因と対策方法
2025/06/01
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。
でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり、整形で受診したら歩くことを勧められて、いざやってみたら膝を痛めてしまったという方もおられるでしょう。
膝を痛めてしまって結局歩くことを断念し、運動しなくなってしまったというのはよくある話です。
では、膝が痛くなったら、あなたならどうしますか?
・しばらく様子を見る?
・湿布を貼る?
・膝をマッサージする?
・整形で痛み止めの注射を打ってもらう?
じつは、これら4つは対症療法なので一時的に痛みが消えても再発する可能性は十分あります。
なので、根本改善にはなりません。
膝を痛めないためには?と言ったら、よく太ももの前の筋肉を鍛えてくださいと整形の先生でもリハビリの先生でもよく話されることです。
しかし、それだけじゃ足りません。
根本改善するなら、付け加えることがあります。
それは、内転筋やハムストリングを鍛えることです。この筋肉がサボって弱っていると、太ももの前の筋肉に負担がかかりすぎてしまい、悪い意味でさらに硬くなってしまい膝の痛みの原因になってしまいます。
なので、太ももの前の筋肉を鍛えるのも大事ですが、内転筋とハムストリング(特に内側)を鍛えることも膝を痛めないように根本改善していく秘訣なのです。
歩行やランニング、スクワットはお尻の筋肉、足の前と後ろの筋肉がメインに働いて鍛えることは可能ですが、日常生活で足の内側の筋肉はあまり使われていないので、内転筋や内側ハムストリングだけは別で鍛えて使える筋肉にしていく必要があるのです。
内転筋の役割
内転筋は股関節を軸にして、太ももを後ろに動かすことと太ももを内側へ動かす作用があります。
内転筋は膝の前を支える太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)の力をサポートするのですが、これがサボってしまうと大腿四頭筋だけが働かせられてしまって、前述した悪い意味で硬くなってしまいます。
そのため、股関節周りの筋肉・そけい部(股関節のつけ根)に炎症が起きて痛みや動かしづらさを引き起こす症状を発症することもあり、膝の内側を痛めたりもしてしまいます。
また、内転筋がサボるとハムストリングが頑張り過ぎて疲れて硬くなることで、内転筋とハムストリングともに動きが悪くなってしまい、太ももの外側の筋肉が頑張り過ぎることで膝に痛みがでてきます。
あと、膝のO脚や尿漏れの原因にもなってしまいます。
ハムストリングの役割
ハムストリングは股関節を軸にして、太ももを後ろに動かすこと、膝を曲げるときに働きます。
ハムストリングは膝の後ろを支える働きがあり、膝の動きは単に曲げる伸ばすだけではありません。ねじれの動きが少しあることで膝は正常な動きになるのですが、これがサボってしまうとねじれの動きがなくなり、単なる曲げ伸ばしの動きになってしまうことで膝の軟骨をすり減らす要因にもなってしまいます。膝の前側と太ももの外側の痛みの原因になってしまいます。
ストレッチで太ももの後ろを伸ばす方法がありますが、ストレッチだけではなく内転筋を鍛えることでも余計な緊張度を下げることができて柔軟性をUPさせることもできます。
最後に、簡単な膝のサボり筋判別方法として、膝を伸ばしたときに痛い場合は内転筋の働きがサボっていて、太ももの前の筋肉(特に外側)、ハムストリングが頑張りすぎて硬くなっている状態です。
反対に、膝を曲げたときに痛い場合は内側のハムストリングの働きがサボって、太ももの前の筋肉(特に真ん中の筋肉)、股関節と膝関節の外側をつないでいる筋肉が頑張りすぎて硬くなっている状態です。
膝の痛み、違和感を根本的に改善したいのなら、ピンポイントでサボり筋を働かせて膝関節が正常な動きができるようにしていくことが痛み症状が戻ってこない方法です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
2024/12/01
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?
股関節のつまりとは?
股関節をまっすぐ曲げた時や股関節をまっすぐ曲げてから太ももを内側に倒したりすると、股関節の前のつけ根につまるような圧迫感、ひっかかりのような感じの状態のことです。
しゃがむ動作で股関節を深く曲げる、座ったまま上半身を捻るなど股関節を内側へ閉じる捻る動作になったときに感じやすいです。
また、つまり感が強い場合は車の乗り降りや階段の上り下りなどでもつまりを感じることがあります。
このつまり感は、股関節周囲の筋肉が硬くなっていることによって起こっています。
しかし、股関節周囲の筋肉が単に硬くなっているだけではなく、股関節周囲の筋肉がバランス良く力を発揮することができなくなり、支えることが弱くなってしまったさぼり筋の影響をうけて、筋肉が過剰に頑張って硬くなってしまっているのです。
筋肉が硬くなってしまうと、股関節の動きが制限されてしまうのでスムーズに動かせなくなってしまい、つまりを感じてしまいます。
つまり感の原因として多いのは、腰椎から大腿骨の内側に着く大腰筋(だいようきん)と骨盤の内側から大腿骨の内側に着く腸骨筋(ちょうこつきん)、この2つの筋肉を合わせた腸腰筋(ちょうようきん)が代表的です。この腸腰筋が硬くなることで大腿神経が圧迫されて、つまるという感覚が起きてしまいます。
股関節がつまる原因は?
・不良姿勢
・運動不足
・立ちっぱなしなど股関節に負担がかかる作業
・股関節の筋力不足
股関節のつまりは、ストレッチに運動をプラスするとさらに効果UP!
SNSでもたくさんのストレッチ方法が紹介されています。
股関節をストレッチすることも大事ですが、もっと効果を出すなら股関節を動かす運動を取り入れるとなお良いでしょう。
①椅子に座って、両方のつま先を内側へ向ける
②両膝の間は、こぶし1個分空けて、太ももの内側を意識してそのまま足踏みをします。さぼり筋改善トレーニングで、さぼり筋が働くようになってくると、硬くなってしまっている筋肉はその影響を受けて頑張りすぎず緩んできてくれます。
股関節は、いくつもの筋肉で支えているので、ひとつでも筋肉が支えることをサボってしまうといろいろな症状が出てきてしまいます。
ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
2024/10/31

10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭痛、めまい等といった症状ありませんか?
病院で診察を受けるほどではないけど、からだの調子がいまひとつ良いとは言えない。
自律神経の乱れは、交感神経と副交感神経のバランスが乱れて生じてしまいます。
自律神経が乱れる原因
1.ストレス
自律神経の乱れはストレスが影響していることが多いといわれています。
なんらかのストレスを受けると、私たちの体はいつも通りの状態を保つためにさまざまな反応をします。
その一つが交感神経を活性化させることです。
ストレスを受けるとそれに対応するために交感神経が優位になり、身体がストレスを乗り切ろうと戦闘態勢になっている状態になってしまいます。
しかし、このような状態が長期間続くと、心身が耐えられる限界を超えてしまい自律神経のバランスが崩れ、不快な症状が出てきてしまいます。
2.不規則な生活習慣
ストレスと並んで自律神経の乱れに影響を与えているとされるのが、生活習慣の乱れです。
睡眠や食事など、昼夜の変化に合わせて体温やホルモンの分泌なども必要に応じて変化させています。
自律神経も同じリズムで働いており、朝目覚めると交感神経が優位に、夕方から夜にかけては副交感神経が優位になります。
しかし、昼夜逆転の生活や慢性的な寝不足、不規則な食習慣、眠る直前までスマホで動画などを見るなどを続けていると、生体リズムが乱れ、自律神経の乱れにもつながります。
3.季節の変化
季節が変化するタイミングで身体の不調を感じる方は多いと思います。
季節の変わり目には気候が不安定だったり、異動や新学期など環境面でも変化が多かったりする時期にも症状がでてきます。
特に、春や秋の気温は昼夜の温度差が10℃もあったりして、気候に適応しようとする身体的な負担、進学や進級、就職や転職など心身へのストレスにつながる要素が多く、自律神経のバランスも乱れやすい時期です。
季節の変わり目は意識して自律神経のバランスを整えるよう心掛けると良いでしょう。
4.更年期障害などの病気
自律神経の乱れはなんらかの病気によって引き起こされる場合もあります。
代表的な病気として知られているのが更年期障害です。
女性ホルモンは脳の視床下部(ししょうかぶ)という場所から指令を受け、卵巣で分泌されます。
しかし、卵巣の機能が衰えると、視床下部からホルモンを出す指令が出てもその通りに卵巣からホルモンを分泌することができません。
そうなると、脳は混乱して「ホルモンをもっと出さなければ」と必要以上の指令を出してしまいます。
自律神経も視床下部によってコントロールされているため、混乱の影響を受けて乱れてしまい、さまざまな症状が起こってしまいます。
また、男性にも更年期障害があり、何らかの理由によってテストステロンの分泌量が減少すると自律神経症状が現れることがあります。
テストステロンの分泌量が減少する理由は、加齢によってテストステロンをつくる細胞が減る、視床下部からの指令が減ることなどが指摘されているほか、ストレスの影響も大きいといわれています。
自律神経の乱れからくる症状は?
・疲れやすい、疲れが取れない
いつもより早めの時間に寝ても疲れが取れておらず、朝から体が重く感じる。
たいして疲れるようなことをしていないのに疲れを感じるといった症状は自律神経からくることもあります。
・首や肩こり、背中がガチガチ
首や肩こりをいつも感じているけど、たいして変わった事もしていなくて、いつも以上にコリを感じる、頭痛、めまいまで出てきたときは自律神経の乱れから来ている場合もあります。
・寝つきが悪い、眠りが浅い、ぐっすり眠れない
日中の緊張やストレス、夜は寝る直前までスマホを見てしまうといった事が、からだの休息モードに切り替わらず、睡眠のリズムが乱れて寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりしてしまいます。
脳が十分に休息できていないまま朝を迎えてしまうので、朝から疲労感を感じてしまいます。
・胃腸の働きが悪くなる
・動悸、高血圧、息切れ、息苦しい
激しい運動をしているわけでもないのに動悸や息切れがする。
脈拍があがったり胸が苦しくなったり圧迫感を感じる。
呼吸をしたときに息が十分に吸えておらず、浅い呼吸になっている。
左胸がズキズキと痛い、針で刺されたみたいにチクチクと痛む。
これらの症状は病院で受診して検査をしても異常がない場合です。
異常がない場合は自律神経の乱れからくる症状の場合もあります。
ストレスで交感神経が高まると筋肉が固くなり、その中を通る血管も細くなってしまい、細くなった血管に酸素や栄養を流すために心臓の拍動が活発になって血液を送り込もうとしするため、動機、高血圧、息苦し
い状態になってしまいます。
・めまい、ふらつき
体や天井、まわりがぐるぐる回る、目がまわるというような回転性のめまいではなく、足が地に着いていないように感じるめまい、ふらつく、姿勢がゆらゆらして保ちにくいといった浮動性のめまいは、自律神経の
乱れからくるものです。
・精神症状
あせりや不安感にかられる。
ちょっとしたことでパニックになる。
冷静になれない、落ち着かない。
やる気がでない。
特に理由はないが、なんとなく憂うつな気分になる。
気分の落ち込み、腹が立ったり、怒りっぽくなるといった感情の起伏が激しくなる。
乱れた自律神経を整えるには?
1.ストレス解消を心がける
心身のリラックスや気分転換になることを取り入れて、ストレスにうまく対処することが自律神経の乱れを整えるための重要なポイントになります。
例えば、整体に行く、散歩や体操などをして体を動かす、趣味を楽しむ時間を持つ、ゆっくりと入浴する、おいしいものを食べたりするなどさまざまな方法があります。
どのストレス対処法が合うかは人それぞれですので、ご自身に合った方法を試してみてください。
2.生活リズムを整える
生活習慣が乱れた状態が続くと、間違いなく自律神経にも悪影響を及ぼします。
食事や睡眠・休息、仕事など昼夜の活動のバランスを意識して、生活リズムを整えることが大切です。
バランスの取れた食事と十分な睡眠をとり、適度な運動は必要です。
そして、仕事を頑張ることは大切ですが、働き過ぎたり無理をしたりしないようにすることも必要です。
生活リズムを整えることは、身体機能を正常に保ち、精神を安定させることにつながります。自律神経のバランスを整えるためには、まずはストレス解消を心掛け、生活リズムを整えることが重要です。
普段の生活を見直して、できるところからはじめてみてはいかがでしょうか?
炭酸水の効果とは?
2024/09/30
-
 ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
-
 股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
-
 膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
-
 アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
-
 インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
糸井中国整体術
当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。
| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |
| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |
| 定休日 | 不定休 |
| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |