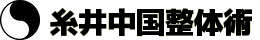小さい子どもから高齢者まで必要な栄養素 カルシウム!
2018/11/01
こんばんは!
朝晩の冷え込みが少しずつ増してきましたね。
そして、食欲の秋ですね。くれぐれも食べ過ぎには気をつけて下さいね!
今日は、出張施術に伺うと高齢のお客様からよく質問されるカルシウムの話をしていきます。
高齢になってくると骨粗鬆症の方が非常に多く、カルシウムの摂取について質問されることが多いです。
日本人のカルシウム摂取量は世界的に見ても非常に不足していて飢餓状態です。糖質や脂質は取り過ぎているんですけどね。
カルシウムのとり方が少なくても、血液中のカルシウムは必ず一定に保つ必要があります。
なぜかというと、血液中のカルシウムが低下すると心臓の動きが悪くなり、脳の働きにも支障がでて、生命の危険が生じるからです。
このため、血液中のカルシウムが少しでも低下すると副甲状腺ホルモンの分泌が増え、骨からカルシウムを取り出して血液中のカルシウムを一定に保とうとするので、骨に蓄えられていたカルシウムはだんだん減少し骨粗鬆症になってしまいます。
カルシウムが不足する大きな原因の一つは、吸収率の低さにあります。
カルシウムをいかに上手に摂るかが不足解消の一歩になるのですが、その吸収率は10〜50%ほどで決して高いものではありません。
また、カルシウムは栄養のバランスによっては吸収を阻害してしまう恐れがあります。
その阻害してしまう栄養素の一つがミネラルの一種「リン」です。
リンはエネルギー産生やDNAの構成成分の一つとして生きていく上で欠かせない栄養素です。
カルシウムとリンは1:1または1:2のバランスを保つことで効率よく働くことができます。
しかし、リンを取り過ぎてしまうとカルシウムの吸収を阻害してしまいます。
リンは多くの食品に含まれているため、普通の食事をしていれば不足することはありません。
しかし、リンは食品添加物として使われる事が多いため、インスタント食品、スナック菓子など加工食品を食べる機会が多い方は取り過ぎに注意が必要です。
毎日の食事でカルシウムを含む食品を積極的に摂り入れることはもちろんのこと、吸収率を良くしてくれる栄養素を一緒に摂るようにすることが大切です。
その栄養素というのが、豆類、魚介類や海藻類に多く含まれているマグネシウム、キノコ類やレバー、青魚、卵に含まれているビタミンD、肉類、魚、卵に含まれている亜鉛などを摂ることで吸収を助けてくれます。
カルシウムが不足していると、骨粗鬆症の他に高血圧、動脈硬化、糖尿病、アルツハイマー病、変形性関節症などの生活習慣病にもかかりやすくなってしまいます。
厚生労働省では、カルシウム摂取量の上限を2300ミリグラムとしていて、牛乳約2リットル分です。結構大変な量だと思います。
カルシウム摂取といえば牛乳を思いつきますが、牛乳嫌いな子どもや乳製品アレルギーを持っている、牛乳を飲むとお腹がゴロゴロするといったことからカルシウムが摂りにくい方もいるので、個人的な意見ですが植物性である豆乳をおすすめします。
それから、ワーファリン(血液抗凝固剤)を服用されている方は、納豆との組み合わせが悪いので注意して下さい。
納豆に含まれているビタミンKがワーファリンの効用を弱めてしまい、その結果血管が詰まって血栓症を発症し、最悪の場合、脳梗塞、心筋梗塞を起こしてしまうので主治医や薬剤師の指示に従ってくださいね。
関連エントリー
-
 ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
-
 股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
-
 膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
-
 アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
-
 インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
糸井中国整体術
当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。
| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |
| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |
| 定休日 | 不定休 |
| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |