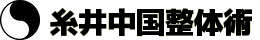- ホーム
- ブログ
ブログ
暑いけど、冷たい飲み物にはご注意を!
2024/08/31
これだけ毎日暑いと、熱中症、脱水症状にならないように水分補給は必要です。
その結果、胃腸自体の調子(便通が悪くなるなど)が悪くなったり、手足の冷え、食欲低下、からだがだるい、むくみ、肌荒れなどの症状が出やすくなります。
胃腸の働きが悪くなるに関連して、股関節を曲げるときに働く腸腰筋(ちょうようきん)という筋肉があります。
これは筋膜を介して胃腸とくっついています。
腸腰筋を鍛えて正常な筋肉の働きができれば、胃腸の働きを正常にすることと合わせて腰痛の改善予防もできます。
反対に腸腰筋の働きが悪いことで、腰痛のほか、腸の活動が悪くなることもあります。話を戻して、日常生活での水分摂取は基本的には「常温の水」がおすすめです。
ただし、冷たい水のほうが効率的な水分摂取になる場合もあります。
運動時の水分摂取は「適度に冷えた飲み物」が適しています。
運動中に大量の汗をかいたときや体温が上がっているとき、脱水症状ですみやかに水分補給をしたいときには、冷えた飲み物で水分補給をしましょう。
ある程度、温度が低いもののほうが胃を速く通過して、吸収スピードが進むと言われています。
ストレッチを少ない努力で効果を得るには、どのくらいやれば良い?
2024/02/01
みなさんは、1カ所の筋肉をストレッチするのにどのくらい時間をかけていますか?
30秒?、1分?、5分?
さすがに1つの筋肉に10分以上ストレッチをするとなると、現実的ではありません。
実際のところ、数分単位ではないでしょうか?
1つの筋肉をストレッチすると、その効果が持続できる時間は概ね5分~30分と言われています。
そして、ストレッチをするのに効果的な時間は60秒を3回以上です。
ガンバって5回っていうところですかね。
では、5分ガンバっておこなうと効果はどのくらいあるかというと、30分ほどの効果が期待できます。
でも、からだが硬い人にとっては60秒を1回するのでもきついですよね。
からだのケアをしなきゃいけないなと思いながらも、明日やろう!と引き延ばしてしまうものです。
私もそんなときがあります(笑)
じゃあ、週に数回のストレッチでも毎日ストレッチするのと同じ効果があるとしたら、ちょっとガンバってみようかなと思ったりしませんか?
結論を言うと、週に3日のストレッチでも毎日のストレッチと同じ効果があります。
週3日ならできそうって思えたなら儲けもんですよ!
さらに、1つの筋肉にストレッチを1回する時間も60秒の半分、30秒を少なくとも3回やっても効果はあります。
そして、少なくとも週3日はガンバルことです。
ストレッチを毎日続けることができれば言うことなしですし、効果的なのもまちがいありません。
でも、人はそこまで強くありません。楽なほうに考えてしまうものです。
最小限の努力で最大の効果を得たいと思うのが正直なところですよね。
良かったら参考にしてみてください。
どのくらい意識してますか?からだのメンテナンス
2023/12/31
みなさんは、自分のからだに気をつかって何か取り組んでいることはありますか?
習慣的にウォーキングやランニングをしている、
ジムに通ってからだを動かしている、
整体やマッサージ、エステに通っているという方、
いらっしゃると思います。
反対に、疲れてそんな余力なんかない~
運動する時間がない~
そんな方へ!
車や機械と同じように、ヒトのからだも定期的にメンテナンスをしたほうが良いですよ!
からだに症状の自覚がなければ何もしなくても大丈夫と思わないでください。
定期的にメンテナンスをする、しないとでは長期的に見て大きな違いが出てきます。
水分、上手に摂れていますか?
2023/08/30
9月になっても暑い日がまだまだ続く予報が出ていますね。
スポーツドリンクと経口補水液の違いとは
スポーツドリンクは、水分、カルシウム、マグネシウム、ミネラルだけでなく、エネルギー源になる砂糖や果糖をからだの中に摂り入れる事ができる飲み物です。どんな時に飲み分けるのが良い?
スポーツドリンクは、水分や塩分だけでなく消費されているカロリーも補えるので、激しい運動や長時間で大量の汗をかいて、塩分やミネラルが失われるような状況の時に飲むのがおすすめです。
経口補水液は、熱中症など軽度から中等度の脱水症状があるとき、ノロウイルスなどの急性胃腸炎、インフルエンザなどにかかり発熱・下痢・嘔吐などによって脱水状態にあるとき、食事の量が少ない(食事を抜く)ことで起こる脱水症状、高齢者が水分をとれないときなどに経口補水液が推奨されています。
飲み過ぎたらどうなるの?
スポーツドリンクはエネルギーを補給するという目的もあるので、糖分が多く含まれています。
水やお茶のように1日を通して少しずつ飲むことで、肥満や糖尿病の原因になるほか、虫歯になる可能性もあるので注意が必要です。
経口補水液は、一時的に大量に飲むことでナトリウムの過剰摂取になり、高血圧になる可能性があります。
高血圧の方や腎臓・心臓などの治療をされている方が日常的に摂取すると逆効果になってしまいます。
健康な人が熱中症対策として、水の代わりに日常的に飲むのにはふさわしくない飲み物です。
飲み方
まとめ
屋内で過ごしていて、食事もちゃんと摂れていてるくらいなら水分補給はお茶や水で良いです。
スポーツをやるとか、大量に汗をかくような場合はスポーツドリンクが良いです。
スポーツドリンクを飲んでいても、熱中症の状態に近づいていく恐れがある場合はスポーツドリンクよりも経口補水液にするほうが良いでしょう。
肩が凝ったら、凝っている所ばかりほぐしていませんか?
2023/08/01
今月は「肩こり」について書いていきます。
腰痛には2つのタイプがあります
2023/06/01これは、腰が反るタイプの腰痛です。
・からだを前屈すると痛い
・からだを左右にねじると痛い
・座ってると痛い
このような場合は骨盤が後ろに倒れて、上半身が後ろへ倒れていかないように背中や腰を丸くしてバランスを取ろうとするため、猫背になり、腰椎のカーブはなくなってまっすぐの状態になります。では、この2つのタイプの腰痛の原因はなんなのでしょうか?
骨盤や腰椎が歪んでいるから?ズレているから?
じゃあ、腰椎や骨盤をボキボキ鳴らして矯正して歪みやズレを治せば良いじゃないと思っている方、非常に多いと思います。
先代の時はそれで一瞬で治った経験のある方も多いと思います。
私も同じように幾度となく腰やあらゆる関節を矯正してもらった経験があるので非常に良くわかりますし、信じていました(笑)
つまり、腰の歪みやズレが原因で痛みが出ているという見解でしたから、関節をボキボキ鳴らして「もう、痛ないやろ?」「腰椎のズレは治ったぞ」で終わっていました。
しかし、よく考えてみてください。
腰が歪んでしまうズレてしまう原因ってなに?って思った方、気づいた方、いらっしゃいますか?
すべての関節にも言えることですが、腰にフォーカスして歪みやズレの原因はなんなのか?をさらに掘り下げると、そもそも腰椎や骨盤が歪んでしまう原因は、腰回りを支えている筋肉が本来の働きをサボってしまい、筋力が低下してしまった結果、腰を構成している骨盤や腰椎の関節を支えきれなくなって歪んだりズレてしまうのです。個人差はありますが、腰をボキボキ鳴らして矯正してもらったけど腰の慢性症状が消えなかったり、痛みが戻ってきたり、ギックリ腰を再発したりしませんでしたか?
それは、間違いなく骨盤や腰椎の関節が歪んだりズレたりして痛みを発しているのではなく、本当の原因は筋力が低下してきてしまった結果、骨盤や腰椎の関節が歪んだりズレたりしているのです。また、多裂筋が弱ると腰の前側の最深部で支えている腸腰筋に過剰な働きをかけてしまうので、過緊張で硬くなってしまいます。
外部からの衝撃で動脈解離を起こす場合もあります
2023/02/24
進展性によるものは、心臓の近くの大動脈で解離が起きた場合、解離の進み具合によっては首にある内頚動脈や椎骨動脈にまで進展することがあります。
特発性は、動脈解離の原因が不明の場合が、これに当たります。
首には脳に血液を送っている動脈が2対あります。
ひとつは首の前側にある頚動脈、もうひとつは首の骨の中にある椎骨動脈です。
頭部では椎骨動脈の解離が最も多く、椎骨動脈が解離すると突然の激しい頭痛を起こします。このときに適切な治療を受け、血管の裂ける程度が軽症で頭痛の症状のみでとどまった場合は、おおむね重大な問題は起こりません。
しかし、血管の裂ける場所や程度によっては、裂けた血管が詰まって脳に血液を送れなくなったり、解離した場所から血栓と呼ばれる血の固まりが心臓付近から首のほうに向かって血管の中を移動して脳血管を閉塞したりして、脳梗塞を起こします。
その結果、運動麻痺や言語障害や嚥下障害などが出現します。
また、血管の壁が外側まで裂けて、血管外に血液が漏れ出ると、くも膜下出血を起こし、激しい頭痛や意識障害が出現して致命傷になることもあります。
また、タバコは脳を含めた全身の血管に最も悪影響を及ぼすので、動脈硬化を進めてしまい動脈解離を起こす確率が上がってしまいます。
関節矯正はからだをすっきりさせる、症状を一瞬で消す万能な手技ではないことを知っていただけたらと思います。
どんなことでもいえることですが、リスクはつきものです。
すっきり爽快感があるからとか、ポキポキ鳴らしてもらうのが良いんだという思い込みなど、安易な理由で関節をポキポキ鳴らす、施術者に鳴らしてもらうのは、からだにはリスクの高い行為になります。
気をつけていただけたらと思います。
足がつりやすくて漢方薬を飲んでるけど効かない!
どうする?
2023/01/25
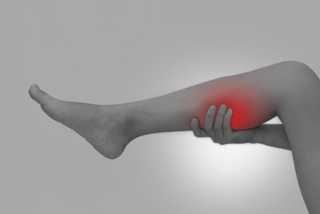
足がつってしまう原因
筋肉は過剰に伸びたり収縮したりすると痛めてしまうので、伸びすぎを防ぐ筋紡錘(きんぼうすい)と、ちぢみすぎを防ぐ腱紡錘(けんぼうすい)というセンサーがあります。
その中で、ちぢみすぎを防ぐ腱紡錘の働きが低下すると筋肉が過剰に収縮して、こむらがえりが発生してしまいます。
ちぢみすぎを防ぐ腱紡錘の働きが低下してしまう大きな原因には、ミネラルバランスの乱れがあります。
筋肉の細胞にはカルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、水素の各イオンバランスが取れていることで正常な伸びちぢみができます。
カルシウム、カリウムは、筋肉の収縮や神経の伝達をスムースにする働きがあり、この2つのミネラルを調整しているのがマグネシウムです。
特にマグネシウムが不足してしまうと、ちぢみすぎを防ぐ腱紡錘の働きが低下してしまいます。
ミネラルバランスの乱れ以外にも、運動中や就寝中の発汗による脱水でミネラルが失われる、体の冷えによる血行不良も、ちぢみすぎを防ぐ腱紡錘の働きを低下させる原因です。
また、加齢によってもちぢみすぎを防ぐ腱紡錘の働きは低下してしまいます。
年齢を重ねると若い頃よりも運動量は減ってくるため筋肉量が減少し、筋力低下を起こしてしまいます。
筋肉量が減ると筋肉内の血行も悪くなってくるため、疲労物質が排出しづらくなり、就寝中にこむらがえりのリスクが高まってしまいます。
足がつらないようにするにはどうすれば良い?
●水分、ミネラルをこまめに補給
運動中や就寝中は水分不足でこむらがえりが発生しやすくなります。スポーツドリンクなどで水分・ミネラルを補給するようにしてください。
また、就寝前にコップ1杯の水を飲むのも有効ですよ。
●栄養バランスに気をつける
マグネシウム不足は腱紡錘の働きを低下させてしまいます。
マグネシウムは、わかめやひじきなどの海藻類やナッツ類に多く含まれています。
カルシウムは、乳製品や大豆製品、魚介類に多く含まれています。
カリウムは、さつまいもなどのイモ類、バナナやキウイなどの果物に含まれています。
また、疲労を回復させるのに、豚肉やうなぎなどに含まれているビタミンB1、レモンや梅干し、お酢に含まれるクエン酸も摂れると良いでしょう。
●からだを冷やさない
冷えは筋肉を収縮させてしまいます。
夏でもパジャマは長ズボンを選ぶ、足にタオルケットをかけるなどしてください。
●湯船につかる
シャワーだけで済ませるのではなく、湯船につかってからだを温めて血行を良くして、疲労物質を流しましょう。
●空いた時間にストレッチ
仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしの方、休憩時間にふくらはぎを伸ばしたりすることも予防になります。
関節トレーニングは関節痛以外にも効果を発揮します!
2023/01/24
施術してもらったときだけ、たまにしかやらない、やり方が間違っていたら効果は期待できません。
セルフケアで関節トレーニングを教えてもらったけど、こんなときはどうすれば良い?
2022/12/25
先月は、働きの悪くなった筋肉に意識を向けてギューっと力を入れる、関節トレーニングのやり方がよくわからないという方のために、コツを5つお伝えしました。
-
 ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
ストレスだけじゃない
昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!
10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭
-
 股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?
座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい
-
 膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
膝が痛い!原因と対策方法
健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり
-
 アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
アイススラリーって知ってますか?
毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ
-
 インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
インナーマッスルが重要な理由
9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について
糸井中国整体術
当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。
| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |
| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |
| 定休日 | 不定休 |
| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |